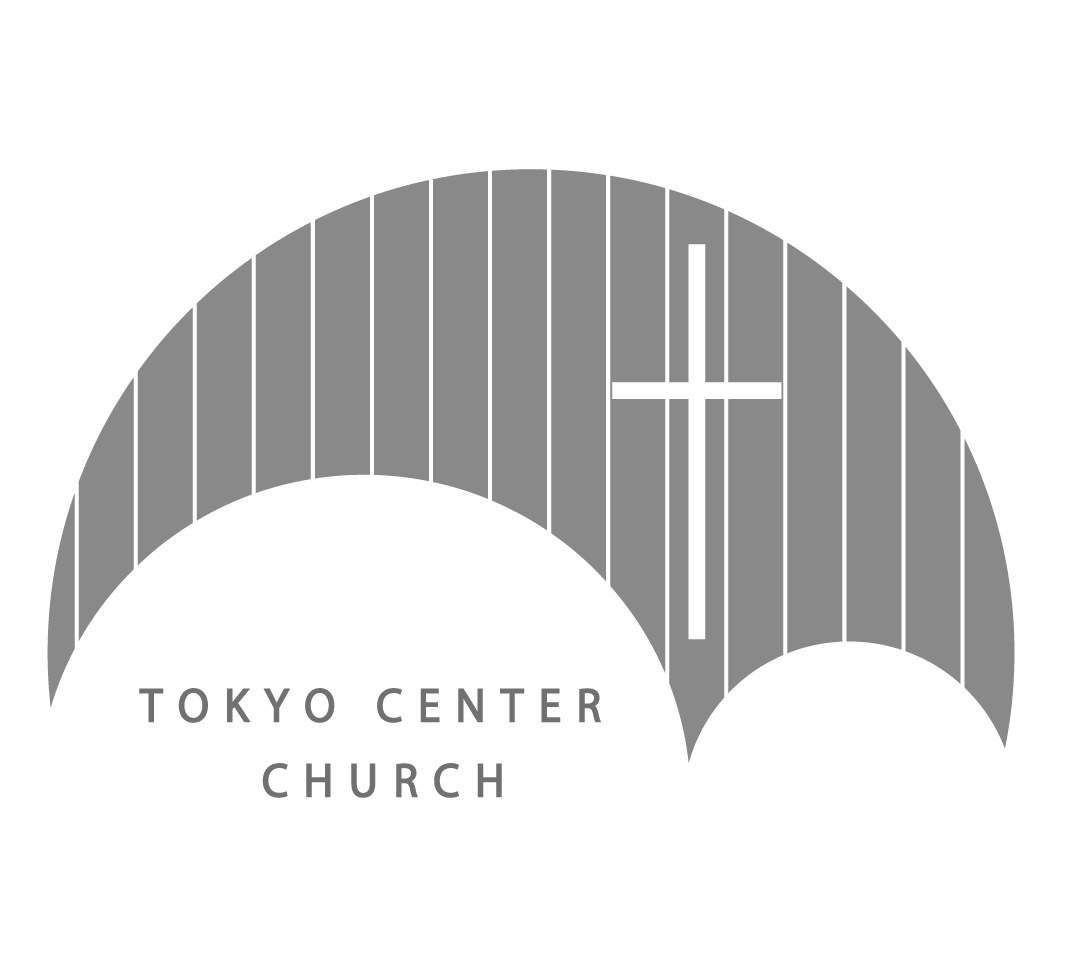2) 橋とらせん
双方向の橋のイメージは大切だ。1970年代に「双方向」が始まったときは、「西洋のキリスト教は正しく、普遍的な表現」という理解だったため、橋を渡る前に微調整するだけ(言葉の翻訳、現地の音楽や服装程度)でOKとの考えだった。また文化はバラバラの風習の寄せ集めで、その一部をはぎ取り置き換えることは可能であり、他の部分は不変でもOK とした。しかしその考えが、西洋の宣教師たちの、自分の神学や実践方法をチャレンジなしに持ち込むという安直な考えを許し、結局は失敗に終わった。
双方向の橋のたとえは、「文脈化」を説明するには不十分だ。橋の両端の権威は同等ではなく、聖書が優れていると、福音伝道者たちは考える。確かに聖書には特別な権威があるのでこれは正しい。もし仮に聖書が「間違い得る」人間の作品なら、文化と聖書は「等しく」権威的であり、相対的となる。となると、結局文化や世代によって、キリスト教は変化しうるし、時代や国が違えば、言うことが矛盾することもありうると判断され、真理を把握することは不可能となる。
この聖書解釈を「双方向」⇒「輪」とする考えの欠点は、聖書と文化を等しく権威的に扱うことは実際上不可能ということにある。聖書のこの部分は正しいが他の部分は時代遅れと言うなら、結局文化が上で聖書はその下ということになる。だから、聖書が最終権威であり、それをもって文化の中のどれが良くどれが悪いかを決める(ケース1)か、文化が最終権威であり、それをもって聖書の中のどれが良くどれが悪いかを決める(ケース2)のいずれかしかない。つまり対称的な橋のイメージは崩れる。われわれは堕落した被造物であり、放っておくと我々は最終的な特権を文化に与えるため、この「輪」は崩壊するのだ。
それゆえ、文脈化は双方向だが最終権威は聖書になければならない。よって今は聖書解釈の「輪」でなく、「らせん」の理解が正しい。もし両者が対等なら、聖書と文脈化の間を行ったり来たりするだけで終わりがないが、「聖書に絶対的な権威がある」となると、行きつ戻りつを繰り返しつつ、神の世界に対する我々の理解が正確となり、その動きはらせん状に「ある特定文化」にしっかりと近づき、その文化と交流することが可能かどうかが明らかになるのだ。
聖書解釈的らせんにより、神学の極端化を防ぐことが可能となる。極端化の一つは原理主義で、それは対象の文化のしばりは受けず、聖書は普遍的な言葉だとする。その逆の極端化は、聖書の神学は、つねに対象の文化による根本概念の範囲の中でしか語れないというもの。福音伝道者は、この中間を求めている。聖書を語るのに、「普遍的な言葉」も「文脈化で調節した言葉」もないが、それにもかかわらず聖書は絶対であり普遍の真理であると。
これを「バランスを取りつつ行う文脈化」という。これが霊的権威の蝶つがいとなり、これにより両極を避け得るのである。
考えよう⇒文脈化を「輪」ではなく、「らせん」で考えることで、どういう変化が生じますか。
3) 聖書の訴え
富める青年、サマリヤの女、ニコデモなど各求道者に対するイエス様のアプローチは全部違っていた。方法論を語り始めるとミニストリーの実は結ばない。逆に自らの文化や気質がどれほど自分のミニストリーに影響しているかに気付くことの方が重要であろう。保守的な気質の人が語る時は、傾向として聖書以上にさばきを強調したくなる。リベラルな気質の人は、聖書以上に無条件の愛を強調したくなる。また物語性を大切にしたい人もいれば、理路整然としたパウロ書簡を好む人もいる。
またノンクリスチャンが信じるに至るモチベーションには次の6通りあるという(D.A カーソン)
- 死と最後の審きへの恐れから信じる (ヘブル2:14-15,18)
- 罪と恥の両方からの解放を求めて信じる (ガラテヤ3:10-12)
- 真理に対する魅力が信仰へのモチベーションとなる (Iコリント1:18)
- まだ成就していない願望が満たされることを通して (ヨハネ4:14-15の生ける水は永遠のいのち以上の約束)
- 問題の解決を通して (マタイ9:20-21長血の女、マタイ 9:27の盲人)
- 単に「愛されたい」という望みから
聖書の著者たちはこの6つの道で人々を説得してきた。ロジカルなものもあれば(真理の魅力)、直感的なものもある(キリストの魅力、欲求の成就)。物語によるもの、ショートターム(必要への満たし)、ロングターム(永遠の審き)といろいろだが、私たちにはこれを決定する権利はない。我々がキリストに導かれたのは、このうちの一つであり、同じモチベーションで導かれた人が同じ共同体に多くいるかもしれず、ゆえにこの「お気に入り」の道で他の人も導こうとするとする傾向があるが、聖書はそんなことは言っていない。その場合我々の説教は十分に聖書的でないことになってしまう。
我々は「聴衆についての知識」に従って、アピールするモチベーションを変更するのだ。福音のメッセージにターゲットの聴衆を引き込む最も効果的な導入があるなら、まずその入り口を提示し、ゆくゆく聖書の語るすべての道を語っていくことがよいと D.A.カーソンは言う。
考えよう⇒あなたは1~6のどれで信じましたか。それ以外の伝道のアプロ―チを訓練することをあなた自身は必要と考えますか
4) アクティブな文脈化
効果的な文脈化に何が必要か?「親しく、尊重と肯定をもってドリルのように文化に入り、聖書的真理に反する部分には発破のように対峙する」がその答えである。もし発破のみなら、「静止摩擦」が生まれず今の流れは止まらず、排除されて終わる。大胆さとすがすがしさは残るかもしれないが、福音の強制力を発揮することはできない。もしドリルのみなら、その文化を肯定し、熟慮し、人々がOKと思うことを言うが、悔い改める人はおこらない。片方ずつでは岩は動かないのだ。信じるところに従って「ドリル+発破」で文化の間違いに挑むなら、福音は人々にインパクトをもたらすだろう。
実際的で、アクティブな文脈化を行う必要があるが、それには3つのプロセスがある。
- 文化に入って行く。
- 文化にチャレンジする。
- 聞く人にアピールする。
これらの3つは互いに絡み合うのだ。
5) 文化に入り、文化に順応する
健全な教義は大切だが、真理は真空に向けて発するのではなく、正直な疑問(希望、反対、恐れなど)に対する正直な回答という形でやり取りされなければならない。つまり真理が特定の人々に向けて発せられるなら、それを通して彼らの文化を知ることになる。同情心を持って聞くことは、文脈化に必要不可欠なアプローチだ。
欧米の宣教師は、韓国の長老教会に、17世紀に英国で作られた「ウエストミンスター信仰告白」を使わせた。
これには先祖や両親、祖父母に対するコメントはほとんどなかったが、家族を尊重し、先祖崇拝をすることは韓国文化においては最重要ファクターだ。もし20世紀の韓国人が自分で「信仰告白」を書いたら、17世紀の英国人とは全く違う質問をしたはずだ。そしてその中から、英国人自身が、自分たちでは気づかなかった新しい視点から、聖書の真理を再発見し学んだことだろう。
6) 文化にどうやって入って行くのか
パウロはアテネの哲学者に語るとき、まず彼らの拝んでいる対象をしっかり調べたが、我々もそれと同じことをする必要がある。専門家の意見を聞くことも、本を読むことも、土地の人と時間を過ごすことも、話を聞くことも効果的だ。ティムケラーがリディーマー教会に赴任したばかりのころ、説教後は必ず聴衆を捕まえてレスポンスを取ったが、「気分を害した」という話を聞いた時、初めて彼らの信念、恐れ、偏見について不注意に語っていたと気づいた。不必要に気を悪くさせていたのだ。この経験は彼の説教準備を変えた。もしすでにその土地の生活や問題、課題に深く入り込んでいるなら、説教準備のために聖書を調べる中で、彼らの質問への神の答えを見いだすことは可能だ。もしその文化に住み、人々と友情を培っているなら文脈化は簡単だとティムケラーは言う。
7) 文化に入り込んだら何を探索すべきか
7-1) ある話を聞き、それへの応答として決定や確信に向かうには、次の3つの道がある。
- 概念的(西洋式):分析と理論による。その前後に前提あり結論ありの、三段論法を好む。
- 実際的、具体的、関係的(中国式):関係性や生活との関連を重んじる。コミュニティーが信じるものを信じ、見たことを信じる。
- 直感的(インド式):洞察と経験から。理論よりもストーリーや物語に力を感じる。
これらの3種類の人たちは次の傾向を持つ。
- 概念的な人々には、神の存在を証明したいという欲求がある
- 実際的な人々は、真実にあまりこだわらず、まず結果に目を留める
- 直感的な人々は、自分の感覚に合わないコミットメントは避ける
聖書の著者はこれらのアプローチの全てを用いている。したがい我々はまず一つの文化に入ったら、今から近づこうとしている人たちにはどのアプローチが有効かを見極めることになる。大まかには、高等教育を受けていない人の方がより実際的、直感的であり、西洋人はそれ以外の人たちより理性的、概念的と言える。
しかし実際の文化はこれほどシンプルでなく、世代別、地域別でも違いがある。
ジョナサンエドワーズは、同じマサチューセッツでも、土地の名士の集まる会堂で説教するときと、アメリカ原住民に向かうときでは、完全に中身を変えた。語る道筋を変えたのだ。後者の会ではポイントを絞り、内容をシンプルにし、物語、例話、隠喩を増やし、三段論法を減らした。イエスの物語を語り、パウロの陳述をやめた。
7-2) 文化に入り込むためには、そこで支配的な世界観、信仰を知ることが必要だ。探すべき信仰は次の2つ:
信仰A:神の一般啓示により、部分的にせよ、すでに彼らが聖書の教えに応答している内容。
信仰B:キリスト教の信仰を信じがたくし、時に攻撃する要素を含む内容。(教義Bはキリスト教の真理と明らかに矛盾する教義となる)
信仰Aは文化ごとに違うため、よく聞く必要がある。そのうえで、この「隠された信仰」を人々に悟らせるのだ。
「あなたの文化にある、この信仰については、実は聖書にも同じことが言われている。いや、もっとはっきり強調されている。」と。パウロはこれをアテネで行った。異邦人の詩から、神の創造と摂理を説いたのだ。このように聖書の真理に対する彼らの敬意を確立することにまず時間を使うのだ。
家族関係やコミュニティーを大切にする文化に対しては、同じ内容が聖書でも言われていることを伝えればよい。
また個人の権利と正義を重んじる文化には、聖書の教義と神のイメージが、歴史的にも理論的にも、個人の権利と正義の概念のベースになっていると言えばよい。この信仰Aが、彼らがジャンプする出発点、文化を変えていく起点となるのだから、これを肯定する必要があるのだ。
8) 文化にチャレンジし対峙する
パウロはギリシア人が知性を重んじ、ユダヤ人が力を愛したことに単純に抵抗するのではなく、「キリスト抜きで力を愛するなら結局は弱さに通じるが、キリストの見かけ上の弱さは真の力をもたらす」と言った。つまり、人の理解の中にある矛盾に光を当て、肯定と対峙をおこなったのだ。チャレンジの前にまず入って行きよく理解することは大切だ。我々が文化に対して批判をするときは、その文化の中で「肯定できる何か」の上に立たないと説得力を持たないし、相手は耳を貸さない。
我々は彼らが正しいと信じている物事の中から語ることで、初めてその信じているものの間違いにチャレンジできるのだ。すべての文化は、独自文化への信仰と、キリスト教信仰のオーバーラップした部分(信仰A)を持つ。
この信仰Aと、敵対的な信仰Bの区別を明確にすることは大切だ。そのことにより、対峙せざるを得ない問題が見えて来るのだ。「教義Aに立って、教義Bについて議論を交わす」がパターンだが、AとBの関係は次の例が分かりやすい。
木は浮き、石は沈む。しかし多くの木を集めてその上に石を置くと、石も木も川を渡ることが可能となる。逆に石を集めてその上に木を置いても、石は沈み、木もばらばらに流れて終わりで、川を渡ることはできない。つまり石は木のうえにおかないとだめで、逆は不可なのだ。このように教義Bは、教義Aの上に載せて運ぶのだ。
ある文化がAを信じるならBを信じないことで矛盾が生じる。それは神の真理である聖書は、決して矛盾しないからだ。文化のはらむこの矛盾は、その文化が対峙を受けたとき、どの部分がもろいかで明らかになる。
パウロはアレオパゴス説教で、異邦人の詩から、「神はすべての存在といのちの源」(使徒17:28) と論じ、そのうえで、「もし、我々が神に造られたのなら、どうして神が我々に造られることになるのか?なぜ我々の用意した宮でのみ礼拝するのか?」(使徒17:29) と問うた。パウロは、彼らの信仰が、彼ら自身の前提と矛盾していることを示した。「もしAを信じるなら、それ自体は正しいことだが、なぜ同時にBが信じられるのか」と。
このように、「あなたはAを信じるのか?それはいいと思う。聖書もそう言っている。でもAは真理なのに、どうしてBを信じるのか?」「聖書はBを教えている。もしAが真理なら、Bを否定することは、正しくないし、フェアーでなく、筋も通らない。」「これを信じるなら、どうしてあれを信じないのか」と。我々の批判の力は、文化の中で肯定する部分を積み上げる中で明らかになって行くのだ。この時の我々の前提は、全て聖書から引き出されるべきである。
考えよう⇒「ドリルと発破」「文化Aと文化B」の組み合わせを、具体的なケースで考えてみましょう